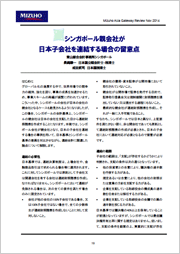シンガポール親会社が日本子会社を連結する場合の留意点
シンガポール親会社が日本子会社を連結する場合の留意点
Aoyama Sogo Accounting Office Singapore
長縄順一 日本国公認会計士・税理士
成田武司 日本国税理士
はじめに
グローバル化の進展する中で、世界市場での競争力の維持、強化を図り、事業の成長を加速させるため、事業スキームの再編が頻繁に行われています。 こういった中、シンガポールの会社が日本の会社の親会社となるケースも散見されるようになりましたが、この場合、シンガポールの会計基準上、シンガポールの親会社は日本の会社を支配した日から連結財務諸表を作成することになります。 本稿では、シンガポール会社が親会社となり、日本の子会社を連結する場合の事例を用いて、日本基準とシンガポール基準の差異を対比させながら、連結会計に関連した論点について解説します。連結の必要性
日本基準では、連結決算制度は、上場会社や、金融商品取引法で求められる場合等に適用されます。これに対してシンガポールでは原則として子会社又は関連会社を有する会社は連結財務諸表を作成しなければなりません。シンガポールにおいて連結が免除される場合は、次の全ての要件を満たす場合のみに限定されています。- 会社が他の会社の100%子会社である場合、又は100%子会社ではない場合で、全ての少数株主が連結財務諸表を作成しないことに対して反対しないこと。
- 親会社の債務・資本証券が公開市場において取引されていないこと。
- 親会社が公開市場で証券を発行する目的で、証券取引委員会又は規制機関に財務諸表を提出していない又は提出する過程にもないこと。
- 最終的な親会社が連結財務諸表を作成し、それが一般に入手可能であること。
すなわち、シンガポールでは日本と異なり、上記要件を満たさない限り、非公開会社であっても原則として連結財務諸表の作成が必要とされ、日本の子会社において連結対応が必要となるので留意が必要です。
連結の範囲
子会社の範囲は、「支配」が存在するかどうかにより判断され、支配の条件は次の通りとなっています。- 他の投資家との合意により、議決権の過半数を行使する力がある。
- 規定あるいは合意により、他の会社の財務または営業の方針を支配する力がある。
- 企業を支配している取締役会の構成員の過半数を任命または解任する力がある。
- 企業を支配している取締役会の会議での票の過半数を投じる力がある。
日本基準では議決権の40%以上を保有していることが前提となっていますが、シンガポールでは最低議決権所有比率に関する規定はありません。従いまして、支配の条件を勘案の上、実質的に支配が存在するか否かを判断することになります。また、シンガポールでは潜在的な議決権も考慮して連結の範囲を決定する点に注意を要します。
決算期及び会計方針の統一
親会社と子会社の決算日は、原則として同一の日でなければなりません。連結対象子会社の決算日が親会社の決算日と90日より大きく異なる場合、グループ全体で決算期を統一しなければならず、たとえ90日以内であっても可能な限り会計期間統一に向けた経営努力を行うことが必要とされています。
日本基準において、子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、限定的な調整を行うことにより、その子会社の財務諸表を連結上も利用することができるものとされています。しかし、シンガポールではそのような規定は設けられておらず、同様の状況における類似する取引及び事象について、全てのグループ内企業の会計方針を統一する必要があります。決算期及び会計方針については、連結会計を行う上で子会社との対応を協議し、どんな体制で行うのかを早期に決めていく必要がある論点となっています。
シンガポール会計基準と日本基準の主な差異
前述の通り、シンガポールと日本の会計基準に差異が存在する場合に会計方針を統一することとなります。以下では、実務上論点として挙がることが多い具体的な差異について確認していきます。- 機能通貨
機能通貨とは、企業が営業活動を行う主要な経済環境で用いられる通貨をいい、日本基準には存在しない概念です。機能通貨の決定のための判断基準は次の3項目を重視して決定されます。
- 財貨やサービスの販売価格に大きな影響を与え、価格表示や決済に用いられる通貨
- 財貨やサービスの販売価格の決定に影響を及ぼす競争勢力や規制を与える国の通貨
- 財貨やサービスを構成する労務費や材料費その他の原価要素を表示し、決済される通貨
つまり、シンガポール親会社と日本子会社で異なる通貨を用いている場合において、連結上ではシンガポールの親会社の使用している通貨を用いて、日本子会社の通貨を換算しなおすことになります
- 収益計上基準
日本基準における収益の認識基準は企業会計原則に規定されていますが、収益認識要件や、実現の定義等については規定されていません。これに対し、シンガポールでは、次の5つの条件を満たすときに収益を認識することとされています。
- 物品の所有に伴う重要なリスクと経済的便益を買い手に移転したこと。
- 販売された物品に対して通常所有とみなされるような継続的な管理上の関与及び有効な支配を保持していないこと。
- 収益の額が信頼性をもって測定可能であること。
- その取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと。
- その取引に関連した原価、発生する原価を信頼性をもって測定できること。
日本の収益認識のタイミングは商慣習等によって異なりますが、実務上は出荷基準、引渡基準又は検収基準等で運用されています。シンガポール親会社が日本子会社を連結する際には、上記5つの条件を厳密に当てはめて、取引の実態に即した収益認識のタイミングを検討することとなります。
- 減価償却費
日本基準においては、著しい不合理がない限り、実務上法人税法に定められた耐用年数、償却方法によって減価償却が行われています。一方、シンガポールでは経済的実態に基づいて減価償却を行う必要があります。また、シンガポールでは有形固定資産の全体の取得原価に関して重要な取得原価を持つ資産項目の構成部分について個別に償却する必要があります(コンポーネント・アカウント)。例えば、船舶の取得原価のうち、船舶の船体部分と エンジン部分は個別に償却するというものです。
シンガポール親会社が日本子会社を連結する際には、日本子会社が行った減価償却がシンガポール会計基準上も認められるかどうかを検討することになります。特に日本基準では、コンポーネント・アカウントについての規定がありませんので、個別に経済的耐用年数を見積もり計算します。
- 有給休暇引当金
日本では、有給休暇に対して費用を認識する基準はありません。一方、シンガポールでは、従業員が勤務を提供した期間の期末後12ヶ月以内に取得することが予測される有給休暇について引当金を認識することが要求されています。これは、企業は従業員から役務の提供を受けた代償として従業員に休暇を付与しているのであり、有給休暇の付与をその役務を提供した従業員に対する給付として認識する、という考えによるものです。シンガポール親会社が日本子会社を連結する際には、日本子会社はこの引当金を計上していないため、重要性を考慮の上、負債として計上することになります。
おわりに
日本基準の細則主義に対し、シンガポール基準は原則主義となっているため、対象となる取引の実態、リスクの所在、権利義務関係を把握し、該当する原理原則に照らし合わせて、経済的実質を最も的確に反映する会計処理と開示の仕方を選択することが肝要です。そして、実務上の調整が多いため、早いタイミングで実務家を含めて会計方針の検討と経理体制の準備が望まれます。長縄 順一
ASA Professionals Singapore Pte.Ltd.(旧社名:Aoyama Sogo Accounting Office Singapore Pte. Ltd.)日本国公認会計士・税理士
慶應義塾大学経済学部卒。1998年監査会社トーマツに入所し、監査業務、株式公開支援業務に従事した後、2001年より青山綜合会計事務所に入所。数多くのファンド組成・管理、クロスボーダー取引へのアドバイザリー業務に携わる。その後、同社にて海事グループ及びグローバル・アドバイザリーグループを統括し、2012年よりAoyama Sogo Accounting Office Singaporeの代表としてシンガポールにて日系企業の海外進出支援業務及び海外ファンド管理業務を担当。
成田 武司
ASA Professionals Singapore Pte.Ltd.(旧社名:Aoyama Sogo Accounting Office Singapore Pte. Ltd.)日本国税理士
明治大学経営学部卒。2005年より会計事務所にて、幅広い業種の事業会社の会計税務業務に従事した後、2011年より青山綜合会計事務所に入所。金融債権・不動産などのストラクチャードファイナンス業務に携わる。その後、2013年よりAoyama Sogo Accounting Office Singaporeにて日系企業の海外進出支援業務及び海外ファンド管理業務を担当。